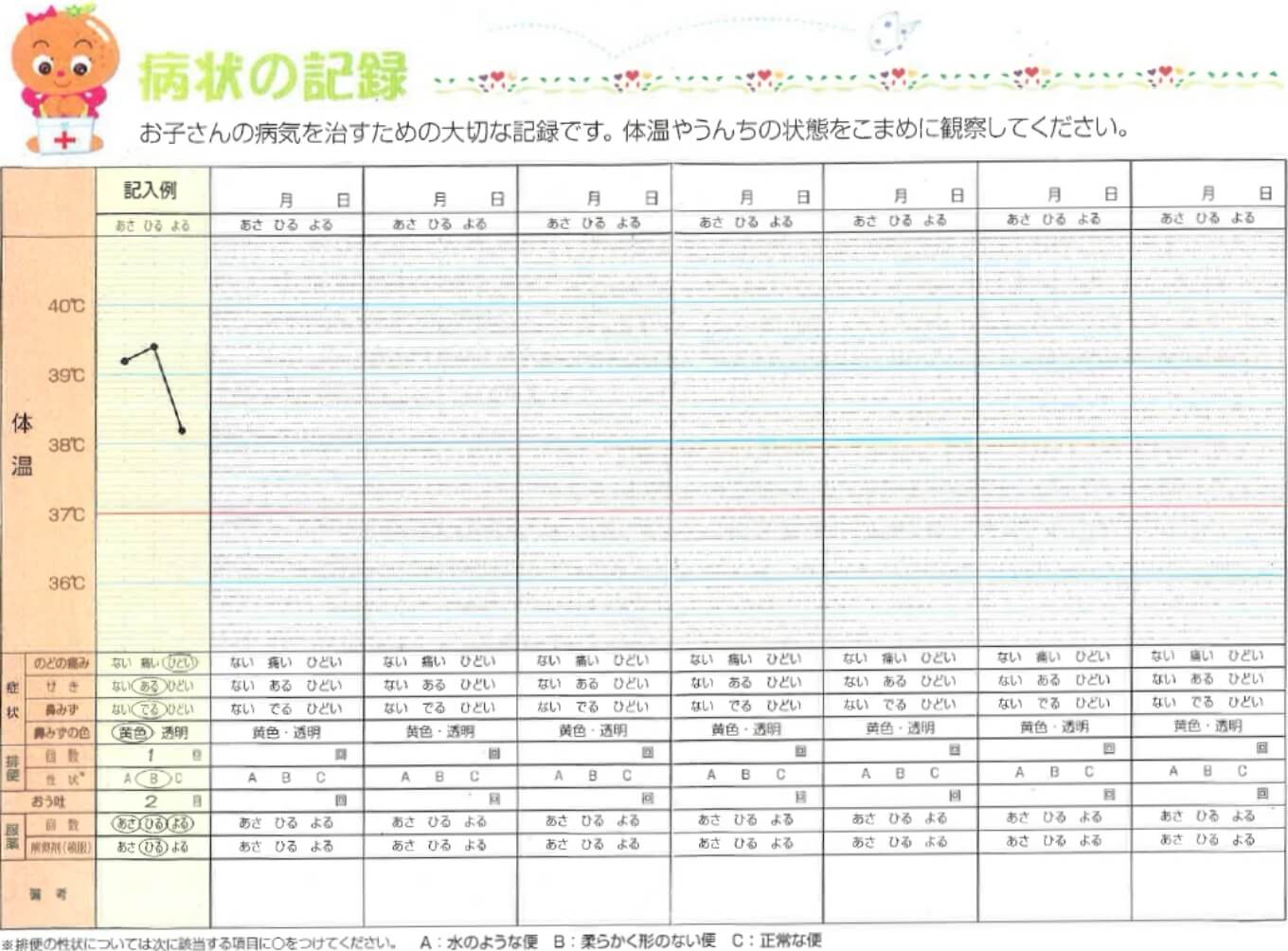今月の独り言
口に入れて飲み込むものは・・・・
ずっと天気の悪い10月でした。秋晴れの日は少なくて、子どもたちの運動会は、延期だったり決行でずぶぬれだったり。暑い日寒い日の繰り返しや、朝夕の温度差も大きく、風邪がはやり、喘息の発作も多い秋でした。
小さいお子さん(3歳以下)は、鼻がかめないのでただの鼻風邪でも、鼻水が増えたりねばこくなったりすると、寝ているときに鼻がつまるし、鼻水がのどに垂れてごろごろと痰がからんで咳になったりして結構大変です。機嫌がよくて眠れていて食欲があれば大丈夫ですが、ちょっと悪化したら早めに診てもらってくださいね。
小さいお子さんといえば、先週参加した小児科の研修会で、小児外科の先生の「異物誤飲」についてのお話を聞きました。1歳前くらいから、子どもはなんでも口に入れるようになります。うっかりするとえらいものを飲み込んでしまいます。とくに、ハイハイやよちよち歩きで自分で動き回るようになる1歳過ぎになると、親が思ってもないものを手にとり口に入れてしまいます。片付けができていなかったりものが散らかったりしていると大変です。この前は、10か月の女の子、いつもお母さんがかわいい髪飾りをつけていましたが、そのかざりのビーズを飲み込んでしまったそうです。髪飾りははずれやすいし、手に取ればまず口に入れる年頃です。親は可愛いと思うおしゃれかもしれませんが、口に入らない大きさのものにしてください。
昔はたばこの誤飲が多く、量が多いとニコチン中毒になるので、病院に来られると胃洗浄といってたばこの洗い出しをしていてなかなか大変でしたが、最近は喫煙率が落ちて、家庭にたばこが減ってきたらしく、誤飲も減ってこれはいいことです。最近は、プラスチック破片やビニール片が増え、ペットボトルの分別回収が進んで、ペットボトルのラベルがはがされると、口に入れる機会が増えているのではないかということでした。
また、いちばんこわいのはリチウム電池だそうです。ボタン電池でいろんな製品に使用されていますが、電圧が高いので、飲み込んで食道にひっかかると1時間くらいで食道に穴があくこともあるそうです。
小さなお子さんをお持ちのご家庭では、部屋を片付けて、ボタン電池の入ってるような製品を子どもの手の届くところにおかない、掃除機をかけて、小さなプラスチックやビニールのごみはないようにしておきましょう。何か口に入れた様子があったり、おえおえと吐くような行動があれば、早く小児科を受診してくださいね。
秋です!喘息と肺炎の季節です
大きな台風が過ぎ去り、秋分の日も過ぎ、だんだん秋めいてきました。
そうなると私たちは忙しくなります。9月になって急に朝夕涼しくなったので、9月の第2週くらいからてきめんに喘息発作が増えました。もともと風邪をひくと喘息がちょっと出る、というような間欠型で、長期管理薬(喘息予防の薬)を飲んでいないお子さんはもちろん、長期管理薬をずっと使っていても発作が出やすくなります。発作治療薬(気管支拡張剤)を短期処方するとともに、長期管理薬を開始する、あるいは追加・増量する、ということが必要になります。午前中の小児科の外来は、吸入・吸引してそのあともう一回診察、という患者さんが多く、なかなか進みません。看護師さんも大忙し、吸入用のマスクがたりなくなって急遽買い足しました。
風邪も増えてきました。喘息発作や、乳児には呼吸不全をおこすRSウイルスも、普通は秋の終わりから冬にかけて流行するのですが、今年は夏の終わりから増えてきて、喘息のある0-1歳の児が何人かRS感染で入院しました。RSではないけど、咳のひどい風邪(おそらくライノウイルス?)も流行っていて3歳以上の幼児たちもけっこう1-2週間咳がひどいです。
9月は今までに当外来から9人が入院しました。これは普通の小児科からくらべると多いと思うのですが、当科はアレルギー専門なので喘息児、および喘息になる体質のある乳幼児の患者さんがもともと多いせいだと思います。それから、初めは普通の風邪で近くの小児科で薬をもらっても、3-4日でよくならないと当科を受診する患者さんも多いのです。本当は、初めに出した薬が効かずに症状が悪化していれば医者はなぜだろうと一生懸命考えて診察して、それが勉強になるので、もとの小児科に行ってもらったほうがいいのですが、患者さんは、よくならなかったら当科に、と決めていらっしゃる方も多く、自然、重症児や合併症の出てきた患者さんが増えます。話を聞いて診察しながら、数分の間に頭ではものすごく急いでいろんなことを考えていて、可能性のある診断や、必要な検査や、お母さんに話さねばばらないことなどをぱぱぱぱぱとチェックしているので、気楽にやっているように見えるかもしれませんが(?)、なかなかこれでも大変神経を使う責任ある仕事なのです。
いますぐ悪化しなくても、今夜・明日はどうなるかわからないのが小さい子の病気の怖いところです。RSの赤ちゃんで二日後に受診したらチアノーゼがあったので急いで処置して酸素を吸わせながら救急車で病院に搬送しましたが、若いお母さんは、赤ちゃんが悪くなっていることがわからないようでした。でも、そうやって子どもの病気を一つずつ見て、考えて、心配して親になっていくのだと思います。がんばれ、お母さん、お父さん!
皮膚をよくして食べて卵アレルギーを予防する
今年の夏はあっという間に過ぎて、気がついたら八月が終わっていました。
開業11年目にして初めて1週間の夏休みをもらいました。海老島先生が来てくれたので余裕ができたのです。あれもしようこれもしたいと思いながらなにもできずに終わってしまいましたが。去年地震で被災した熊本の実家はとうとう取り壊しになり、ちょっとつらい夏でもありました。
さて、最近小児アレルギー学会から、鶏卵アレルギー予防に関する提言、というのが出されました。乳児のアトピー性皮膚炎では、かなりの率で卵アレルギーが発症します。実際に食べてアレルギー反応が出れば卵アレルギーなのですが、血液検査で卵のIgE値がちょっと上がっているだけでも、食べたらアレルギー反応が出るかもしれないから、やめておきましょうというのが20年来の考え方でした。しかし最近わかってきたことは、皮膚状態が悪いとバリア機能が低下して、経皮感作といって、皮膚からアレルゲンが入ってIgE抗体を作るということです。そしてそれが本当に食べてアレルギー反応をおこすかはまた別だということです。
最近日本から出た研究が世界的な雑誌に載りました。生後4-5ヶ月でアトピー性皮膚炎のあった乳児を、皮膚の治療をしながら、60人には生後6か月から毎日、微量の加熱卵を与える。別の61人は卵を与えない。そして1歳になったところで卵半分の負荷試験をすると、卵をずっと与えていた群では8%の子が卵アレルギーだったのですが。食べさせていなかった群では38%が卵アレルギーでした。つまり、食べさせたほうが卵アレルギーは予防できる、という結果だったのです。
これを受けて学会は、「乳児期のアトピー性皮膚炎のある子は」「皮膚の治療をしてよくなってから」「6か月から少量の加熱卵(ゆで卵白0.2gくらいだそうです)を毎日」「与えることで卵アレルギーを予防できる」という提言を出したのです。もちろん卵を与えて症状が出た子は対象になりません。
しかし実際にこういう指導が一般小児科で責任もってやれるかどうかというのが心配されていて、どうなっていくのか、次回の学会で論議になりそうです。

 待ち時間
待ち時間 TEL
TEL